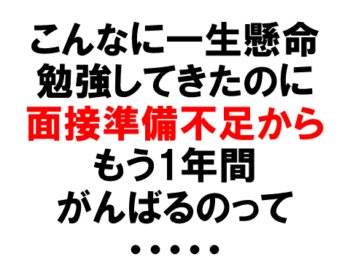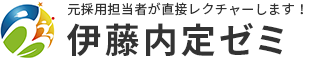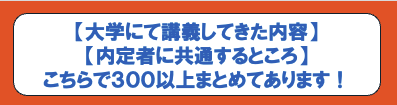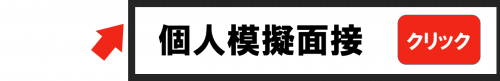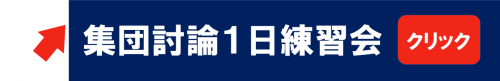集団討論役割:発表者

集団討論において
警察官採用の場合には、発表のないところも多いです。
その理由は、討論内でどれだけ論理的な意見を言えるかどうかがポイントだからです。
市役所や県庁の採用選考集団討論では、最後にグループとしての発表がある場合が多いです。
その理由は、市役所では、市民に説明しなければいけないことが多く、プレゼンテーション能力も求められる能力の一つだからです。
県庁でも同じです。県庁では、直接県民に説明する機会は少ないかもしれませんが、市役所の担当職員や下請けの民間企業に説明する機会もあるからです。
集団討論の練習会で、発表者に教えていることは、3つあります。
①語りかけるように発表する。
②笑顔で、全員の顔を見て発表する。
③簡潔に結論と根拠を述べる。
少し、慣れと言い方のポイントが必要ですね。
地方公務員として、
・政策を作る人もいれば
・地域住民の中でリーダーシップをとって住民を巻き込むリーダーシップのある方
・住民に対し、説明力が高くプレゼンテーションができる方
等々、求める人物があります。
・司会者を担当すれば、⇒住民を巻き込むリーダーシップがありそうだと面接官の仮説が立ち、
・結論をまとめることができれば⇒問題解決の政策立案等ができそうだと面接官の仮説が立ち、
・発表がうまければ、住民への説明を任せても大丈夫だ⇒のように、活躍すると面接官の仮説が立ちます。
おススメは、個人的な見解ですが司会者よりも、発表者です。
その理由は、説明する力が弱いと周りを巻き込んで仕事をできないからです。
次の記事はこちら
集団討論の流れ
集団討論役割:司会者
集団討論役割:タイムキーパー
集団討論役割:メンバー
ぜひ、集団討論1日練習会を受けて実際に学んでくださいね。
集団討論1日練習会